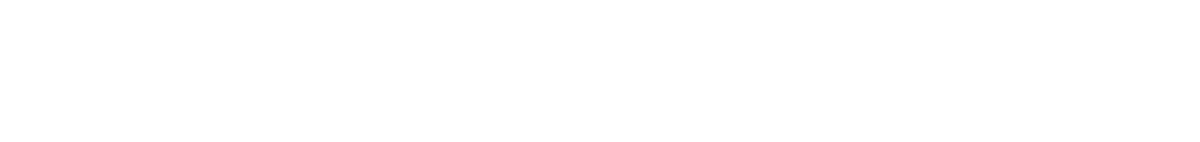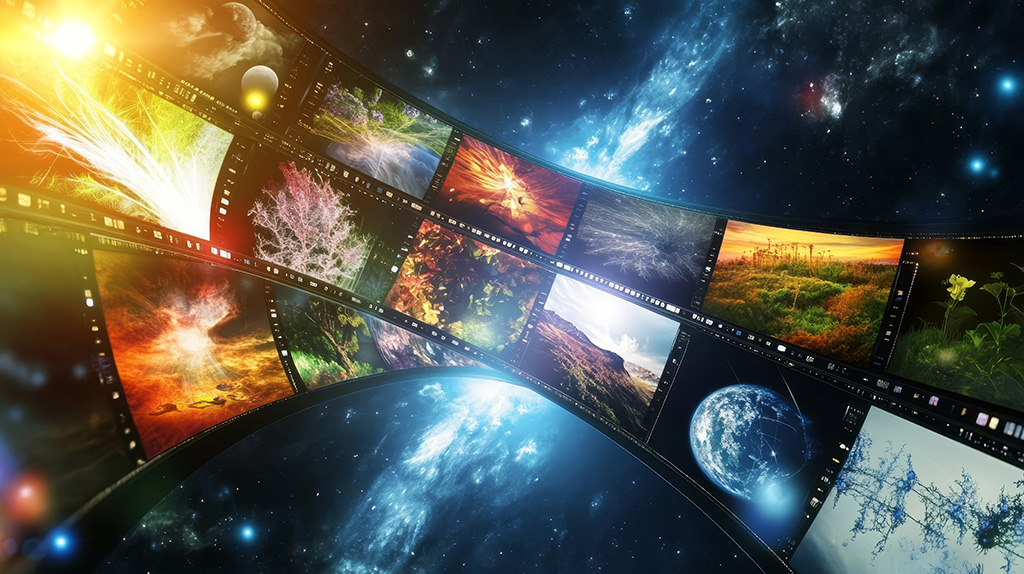「天の音楽」が現実になる時
イントロダクション
17世紀の天文学者ヨハネス・ケプラーは、惑星の軌道を「天の音楽(Musica Universalis)」と呼びました。彼にとって宇宙は、沈黙の空間ではなく、神の調和が奏でる壮大な交響曲だったのです。惑星の運行には比率とリズムがあり、それは数式であり、同時に“音”でもある――この思想は後に科学と芸術の両方に深い影響を与えました。
それから400年。私たちは望遠鏡や探査機によって宇宙の実像を知りながらも、映画というメディアを通じて、今なお「宇宙の音」を夢見ています。真空の宇宙には音は存在しないはずなのに、なぜ映画では壮大な音楽が鳴り響くのでしょうか? その問いは、宇宙をどう感じ、どう理解してきたかという人類の想像力の歴史そのものを映し出しています。
本稿では、宇宙映画に用いられた音楽の変遷をたどりながら、宇宙映画がどのように“音のない宇宙に音を与えてきたか”を考えていきます。
神話の音楽:オーケストラが描く“秩序ある宇宙”
宇宙SF映画における音楽の歴史は、まず何よりも「オーケストラの響き」から始まります。まだ電子音が一般的ではなかった1950〜60年代、宇宙は“理性と秩序の象徴”として描かれていました。音楽はその理念を支える柱であり、壮大な弦と金管の響きが「宇宙=神の設計図」であるかのように響いていたのです。
その代表が、スタンリー・キューブリック監督の『2001年宇宙の旅』(1968)です。この作品では、リヒャルト・シュトラウスの《ツァラトゥストラはかく語りき》が人類の進化を告げ、ヨハン・シュトラウスの《美しく青きドナウ》が宇宙船の軌道を優雅に描き出します。まるで宇宙全体がひとつの交響曲のように響く――そんな体験を映画史上初めて与えた作品でした。ここで音楽はBGMではなく、宇宙そのものを表現する媒体になったのです。
一方で、アメリカのテレビシリーズ『スタートレック』(1966〜)でも、同じようにクラシカルな音楽が理想主義的な未来像を支えていました。U.S.S.エンタープライズ号が星々をめぐる冒険を始めるとき、バックにはトランペットが高らかに鳴り響く。そこには「人類の探究心」や「理性による調和」への信頼がありました。音楽が壮大であればあるほど、宇宙は安心できる場所に聞こえる――そんな時代だったのです。
このオーケストラ主導の宇宙像を、20世紀後半に再び復活させたのが『スター・ウォーズ』(1977)でした。ジョン・ウィリアムズの手によるテーマ曲は、クラシック黄金期のハリウッド・サウンドを現代に蘇らせ、人類の“宇宙神話”を再構築しました。シンセサイザーが流行していた70年代に、あえてフルオーケストラで挑む。その逆行的な選択が、結果的に観客の心をつかんだのです。
機械の音楽:電子音が奏でる“未知と不安”
シンセサイザーの登場以降、映画の宇宙からオーケストラが消えていきます。かわりに現れたのは、人間が理解しきれない音――電子音、ノイズ、そして不穏な低周波の震えでした。宇宙はもはや理想の舞台ではなく、「未知への恐怖」と「テクノロジーの孤独」を鳴らす場所になっていきます。
その先駆けとなったのが、1956年の『禁断の惑星(Forbidden Planet)』です。作曲を手がけたのは、ルイス&ベベ・バロン夫妻。彼らは世界で初めて、電子回路そのものを“楽器”として扱いました。抵抗や真空管の偶発的なノイズを録音し、それを切り貼りして音楽を構成する――つまり、人間の意図ではなく機械が生み出す偶然の音が宇宙の声として鳴り響いたのです。当時の観客は、それを「音楽」と呼んでいいのかすら分からなかったといいます。
その後、電子音は冷戦期の不安や、テクノロジーへの不信を象徴するようになります。アンドレイ・タルコフスキーの『惑星ソラリス』(1972)では、バッハのオルガン曲が人間の記憶を象徴する一方で、電子音が宇宙そのものの「無意識」を表現しました。電子音は、理解不能な宇宙との“対話不能性”そのものを聴かせているのです。
この流れをさらに美しく深化させたのが、ヴァンゲリスの『ブレードランナー』(1982)です。ここで電子音はもはや機械的な冷たさではなく、都市の呼吸として機能します。アナログ・シンセサイザーの音が雨音やネオンの光と混ざり合い、未来都市ロサンゼルスを幻想的に包み込みます。そこにはもはや神も理性もなく、ただ機械と人間が混ざり合った“曖昧な世界”が響いている。オーケストラの時代が描いた「秩序ある宇宙」とは対照的に、ヴァンゲリスの宇宙は感情を失った地上の延長なのです。
沈黙の音楽:無音が語る“宇宙の恐怖”
宇宙に本来「音」は存在しません。真空では空気が振動しないからです。にもかかわらず、映画の中の宇宙はずっと“鳴り続けて”きました。ところが1979年、『エイリアン』がその常識を覆します。あの有名なキャッチコピー――“In space, no one can hear you scream.”(宇宙では、あなたの悲鳴は誰にも聞こえない)。それはまさに「音のない恐怖」を宣言する言葉でした。
リドリー・スコット監督はドルビー・ステレオという新しい音響技術を使い、音を“増やす”のではなく、“消す”方向に使いました。USCSSノストロモ号の内部では、金属のきしみ、呼吸音、遠くで鳴る警告音がリアルに響きます。しかし一歩、宇宙空間に出れば音は完全に途絶えてしまうのです。その対比が、観客の無意識に“死”の静けさを刻みます。音楽ではなく、無音が物語を語る――それが『エイリアン』の革新でした。
この「沈黙の美学」はその後の宇宙映画にも大きな影響を与えます。たとえばロン・ハワード監督の『アポロ13』(1995)では、実際のNASA通信音声が緊迫感を作り出し、ハンス・ジマーらのドラマティックなスコアはあえて控えめに扱われました。音を足すのではなく、“音を削る勇気”がリアリティを生む――この発想が宇宙映画の新しいリアリズムを確立していきます。
その到達点ともいえるのが、アルフォンソ・キュアロン監督の『ゼロ・グラビティ(Gravity)』(2013)です。宇宙飛行士ライアン(サンドラ・ブロック)が漂う無音の宇宙を、作曲家スティーヴン・プライスは「音の無さを音楽で描く」という逆説的な手法で表現しました。電子音とオーケストラを絶妙にブレンドし、振動や呼吸のリズムがそのまま音楽の構造になる。宇宙そのものが“楽器”のように聞こえる瞬間です。
『エイリアン』の沈黙が「恐怖の空間」を作り、『グラビティ』の沈黙が「生の実感」を作る。どちらにも共通しているのは、音が減るほど、観客の身体感覚が研ぎ澄まされていくということです。人間が作る音が消えたとき、私たちは初めて“宇宙の本当の音”――すなわち、心臓の鼓動と呼吸のリズム――に耳を澄ませることになるのです。
人間の音楽:感情と記憶のこだま
2000年代以降の宇宙映画では、音楽が再び“人間のための音”を取り戻し始めます。冷たい電子音や沈黙のリアリズムを経て、再び人の感情に寄り添う音が戻ってきます。けれどもそれは、かつてのような単なるオーケストラの壮大さではなく、「科学と感情の交差点」で鳴る音へと変化していました。
ハンス・ジマーが手がけた『インターステラー』(2014)は、その象徴的な作品です。音楽の主役は、なんと教会のパイプオルガン。古代から“神の声”とされてきたこの楽器が、重力と時間のドラマを包み込みます。ジマーはこの映画のために、最初に脚本ではなく“テーマ”だけを監督ノーランから受け取り、「愛する者のために旅立つ音」を作曲したといいます。結果として、宇宙の冷たさと人間の祈りが共鳴するようなサウンドが生まれました。
一方で、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』(2014)はまったく異なる方向から“人間の音楽”を取り戻しました。宇宙を駆けるヒーローが再生するのは、70年代のポップスやロック。デヴィッド・ボウイ、マーヴィン・ゲイ、フリートウッド・マック――これらの楽曲は、最新の宇宙船よりも懐かしい人間の温度を運びます。音があるから、宇宙に孤独を感じない。音楽は「人間であること」の証として響いています。
こうして現代の宇宙映画では、音楽は再び人間の中心に戻ってきました。ただしそれは、もはや人類の勝利を高らかに歌い上げるものではありません。むしろ、宇宙の沈黙の中に小さく灯る人間の声として響いているのです。
宇宙に「音」を与えた人間たちの歴史
「宇宙には音がない」と、私たちは知っています。けれど、宇宙映画の歴史を振り返ると、人類はあらゆる手段で“音”をそこに響かせてきました。オーケストラで神の秩序を描き、電子音で未知の不安を震わせ、沈黙で現実を突きつけ、そしてポップスやオルガンで再び人間の感情を取り戻す。そうして見えてくるのは――音こそ、人間が宇宙を理解しようとする方法そのものだということです。
今やAIが音楽を生成し、宇宙探査機が実際の星の振動データを“音”に変換する時代になりました。人間はもはや想像だけでなく、現実の宇宙から音を聴き取ろうとしています。もしかすると私たちは、何千年もかけて「宇宙の沈黙に言葉を与える」旅を続けているのかもしれません。
映画の中の宇宙が鳴り続ける限り、それは単なる幻想ではありません。音がある限り、宇宙は無ではない――宇宙SF映画はそんなことを私たちに教えてくれます。