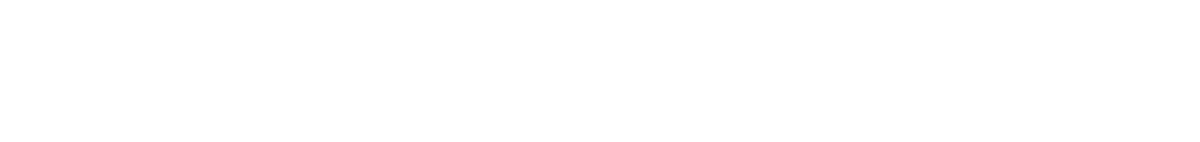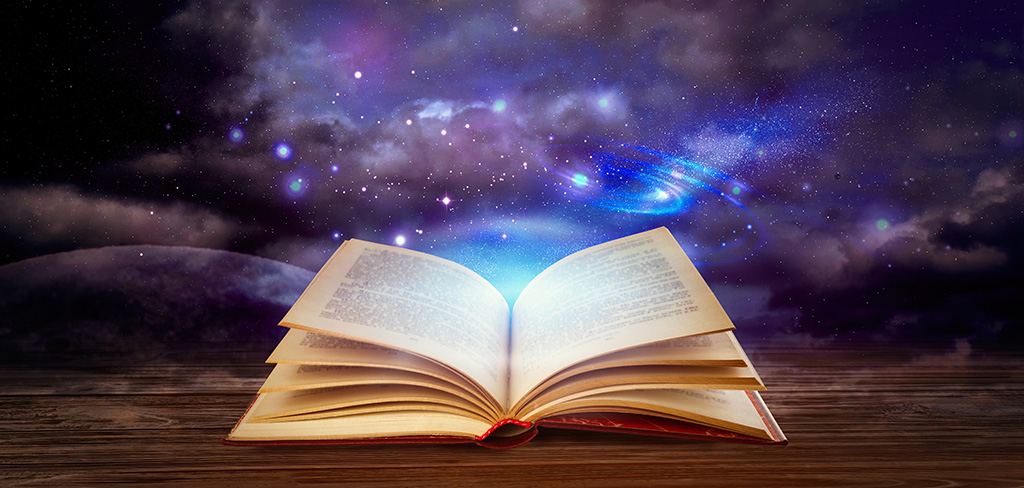イントロダクション:SFにおける黒人、女性、マイノリティ
マーベル映画『ブラックパンサー』で描かれたアフロフューチャリズム的な世界観や、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』の多様な種族が集まったクルーたちを思い出すと、SFと多様性は切っても切り離せない関係にあることを実感します。宇宙を舞台にした物語は、しばしば「本質的に異なる存在同士が、ともに生きることは可能なのか?」という問いを突きつけてきました。そこには、差別や抑圧の再生産が潜んでいることもあれば、異質な者どうしの協働によって新しい可能性が生まれることもあります。
白人男性が中心に描かれてきたSFの長い歴史の中で、黒人や女性、さらには性的マイノリティの作家やキャラクターがどう居場所を獲得してきたのか。その歩みをたどることは、「宇宙における多様性」を考える上でとても示唆的です。差別の歴史を背負いながらも、新しい形のアイデンティティや共生の姿を描き出してきた作品たちは、私たちに「違い」をどう捉えるべきかを教えてくれます。
今回はそんなテーマにぴったりな4作品――シオドア・スタージョン『人間以上』、サミュエル・R・ディレイニー『ノヴァ』、オクタヴィア・E・バトラー『血をわけた子供』、そしてN.K.ジェミシン『破壊された地球』三部作――を紹介していきます。
シオドア・スタージョン『人間以上』(1953)
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784150103170
シオドア・スタージョンといえば、40〜50年代のアメリカSFを代表する作家のひとり。彼の代表作『人間以上(More Than Human)』は、1954年に国際幻想文学賞を受賞した古典的名作です。
物語に登場するのは、社会の中で居場所を持てない「はみだし者」たち。白痴と呼ばれる青年、生意気な幼女、言葉を話さない双子、そしてダウン症の赤ん坊。それぞれが孤立し、周囲から拒絶されながらも、実は特異な能力を秘めています。そして彼らが出会い、力を合わせることで「ホモ・ゲシュタルト(Homo Gestalt)」と呼ばれる新しい存在、つまり“ひとりの個人を超えた人類の次の段階”へと進化していくのです。
この小説の魅力は、超能力や進化をモチーフにしつつも、単なるスペクタクルでは終わらないところです。スタージョンが描くのは、「異なる者どうしが結びつき、協力し合うことで初めて拓かれる可能性」。つまり、多様性が単なる相違や分断ではなく、むしろ人類の未来を形づくる力になり得る、という視点です。
『人間以上』を読むと、異質な存在を排除する社会ではなく、異質さを受け入れて結び合わせる社会こそが未来を切り開くのだという、普遍的なメッセージが浮かび上がってきます。今あらためて読む価値のある、柔らかくも深い一冊です。
サミュエル・R・ディレイニー『ノヴァ』(1968)
https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784150115395
サミュエル・R・ディレイニーの代表作『ノヴァ』は、ハーマン・メルヴィルの『白鯨』を宇宙規模に翻案した野心作です。船長、乗組員、芸術家としての語り手、大海に相当する宇宙、探求の旅、百科全書的な知識の蓄積――こうした『白鯨』の要素が緻密に組み込まれています。ただし、鯨はここでは「不在の象徴的物質」として描かれ、人類が追い求める究極の対象へと姿を変えています。
この作品が特に斬新だったのは、人種的に多様なクルーと黒人主人公を前面に据えたことでした。当時のSF界は白人作家・白人キャラクター中心の世界であり、その中にディレイニーが投げ込んだ『ノヴァ』は強烈な衝撃を与えました。実際、1967年に本作を雑誌連載に持ち込んだ際、編集者ジョン・W・キャンベルは「読者は黒人主人公に共感できないだろう」として掲載を拒否したエピソードが残っています。これは、SFの舞台が宇宙へと広がってもなお、人種的な偏見が現実的に存在していたことを示しています。
ディレイニーは、自分の小説を「自分の人生に対しておこなう絶え間ない注釈」だと語りました。『ノヴァ』もまた、黒人であり、ゲイであり、言語や文化にまたがって生きる彼自身の経験を投影した作品です。SF、ファンタジー、リアリズム、批評を横断する作家の筆致は、単なる冒険物語にとどまらず、人種・ジェンダー・言語の交差から普遍を探る文学的実験として輝きを放っています。
オクタヴィア・E・バトラー『血をわけた子供』(1984)
https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309208558
オクタヴィア・E・バトラーは、アメリカ本国では高く評価されながら、日本では長らく知られることの少なかったSF作家です。女性であり、黒人であるという二重の意味で先駆者的な存在で、彼女の作品はジェンダーや人種、権力関係を鋭く描き出しています。
短編集『血をわけた子供』には、7つの短篇と2つのエッセー、さらにそれぞれの作品についての著者自身による解説が収められています。表題作「血をわけた子供」は、1984年にヒューゴー賞、ローカス賞、SFクロニクル賞を受賞した代表作。ムカデのような姿をした異星種族トリクと、彼らの惑星に移住した人間との共生関係を描いています。トリクは人間の体内に卵を産みつけ、人間はその代わりに保護を受ける――という設定は、一見すると奴隷制の寓話のようにも思えます。しかしバトラーは「これは奴隷制の物語ではない」と明言しています。
物語の中で卵を宿すのはむしろ男性であり、これは「困難な状況で男性は愛のために妊娠を選ぶことができるか?」という問いを投げかけています。さらに別のレベルでは、これは異なる種族同士のラヴストーリーでもあります。けれども、その共生は決して明るく理想的なものではなく、むしろ読者に強い不安と緊張を残します。この「居心地の悪さ」こそが、バトラーの物語の力なのです。
他にも、遺伝子疾患の絶望を描きながらわずかな希望を示す「夕方と、朝と、夜と」や、疫病によって言語を失った人類を描く「話す音」など、短いながらも読後に長く残る物語が収録されています。どの作品も、暴力や支配の影をはらみつつ、それでも人間の関係性や希望の可能性を模索し続けているのです。
バトラーの作品は甘美な夢ではなく、現実の矛盾や痛みをえぐり出すことで、多様性と共生の難しさを突きつけるものです。そこにこそ、彼女の小説が現代にも強く響く理由があります。
N.K.ジェミシン『破壊された地球』三部作(2015–2017)

N.K.ジェミシンの『破壊された地球』(The Broken Earth)三部作は、史上初めて三年連続でヒューゴー賞を受賞した金字塔的シリーズです。その第一部『第五の季節』は、文明が周期的に崩壊する過酷な大陸〈スティルネス〉を舞台に、人々がどのように生き延び、どのように抑圧と差別に向き合うかを描いています。
この世界では数百年ごとに「第五の季節」と呼ばれる大規模な天変地異が発生し、人類を何度も絶滅寸前に追いやってきました。人々はその訪れを前提に食料を蓄え、都市を要塞化し、文明を細々とつないでいます。その中で、地殻の熱や運動エネルギーを操る力を持つ「オロジェン」と呼ばれる人々が存在します。彼らは地震や火山噴火を制御できる一方で、その力の暴走は周囲を壊滅させてしまう危険もはらんでおり、社会からは恐れられ、監視され、時に迫害の対象となってきました。
三部作の物語は、三人の女性オロジェンの視点から描かれます。息子を夫に殺され、娘を奪われた母エッスン。両親に疎まれ、〈守護者〉に引き渡される少女ダマヤ。帝国に仕えるオロジェンとして、望まぬ任務や強制的な繁殖を強いられるサイアナイト。それぞれが異なる形で抑圧されながらも、「生き延びる」以上の、「どう生きるか」という問いに直面していきます。
このシリーズの凄みは、壮大な世界観と極限のサバイバル劇の中で、人種差別・性差別・支配構造といった現実社会の問題を重ね合わせている点にあります。オロジェンたちが差別される構図は、現実のマイノリティが置かれてきた状況を鮮やかに映し出し、同時に「共に生きるとはどういうことか?」を読者に突きつけます。
ジェミシン自身はこの作品を「ファンタジー」と呼んでいますが、能力の理屈や社会の制度設計には緻密なロジックがあり、SF的な思考実験としての厚みも十分。神話と科学、破壊と再生、差別と連帯――それらが重層的に絡み合うことで、この作品は単なる「破滅小説」ではなく、現代社会を読み解く比喩として輝きを放っているのです。
『破壊された地球』三部作は、宇宙規模の視野で「多様性」と「共生」の可能性を描き切った、まさに21世紀のSFを代表する傑作と言えるでしょう。
最後に:宇宙は多様性の実験場である
ここまでご紹介した作品は、いずれも多様性とアイデンティティをめぐる実験の場として「宇宙」を活用していました。
SFにおける宇宙は、単なる冒険の舞台や科学的なフロンティアではありません。そこは人種・性別・身体・文化といった境界が問い直され、新しいつながり方や社会の形を試みる「実験室」なのです。
現実社会では多様性がしばしば摩擦や対立を生む一方で、SFの物語はそれを「衝突の先にある可能性」へと変換してきました。異なる者同士がともに生きることは簡単ではない、時に痛みや犠牲を伴う――それでもSFは、その難しさを直視しつつ「別の世界」を構想し続けています。
だからこそ、宇宙を舞台にしたこれらの物語は、単に未来を夢見るだけでなく、いま私たちがどう生き、多様性をどう受け止めていくかという切実な問いを投げかけてくれるのです。