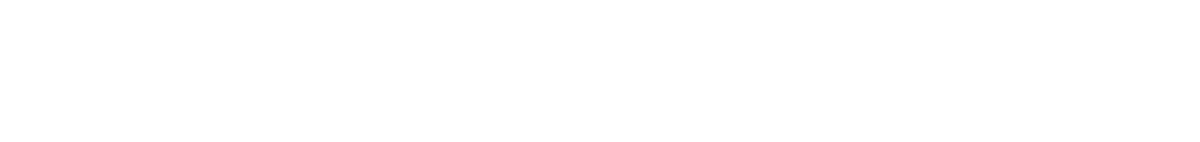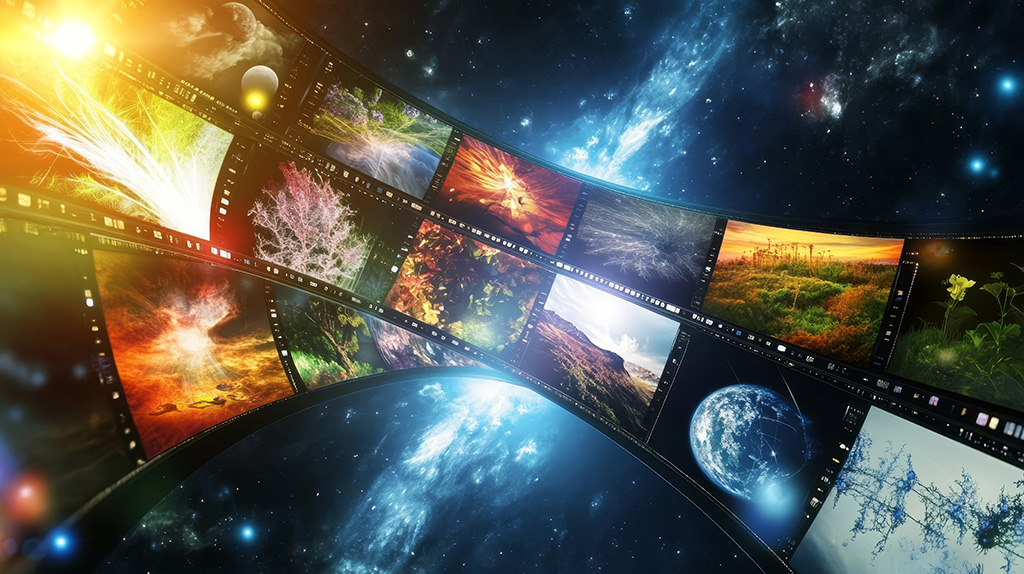「理想主義」デザインと「現実主義」デザインの対立の50年
イントロダクション
これまで本連載では、様々な切り口から宇宙SF映画をご紹介してきました。今回は少し趣向を変えて、「デザイン」という視点から宇宙SF映画を見つめ直してみたいと思います。取り上げるのは、「映画に登場する宇宙船」です。
1960年代、『2001年宇宙の旅』のディスカバリー号や『スタートレック』のエンタープライズ号に代表される宇宙船は、滑らかで、合理的で、完璧な秩序に満ちていました。それは、科学の進歩を人類の希望と信じて疑わなかった時代の産物であり、本稿ではこれを「理想主義デザイン」と呼ぶことにします。
しかし、1970年代後半になると、『スター・ウォーズ』のミレニアム・ファルコンや『エイリアン』のノストロモ号に象徴されるように、宇宙船は一転して錆びつき、汚れ、修理を重ねた「現実主義デザイン」へと変化します。宇宙はもはや理想郷ではなく、労働と生活の場となったのです。
本稿では、この理想主義デザインと現実主義デザインの対立を軸に、宇宙映画における宇宙船デザインの変遷をたどります。1960年代の科学的楽観主義から、1970〜80年代の工業的リアリズム、そして21世紀における人間的理想の再構築へ――宇宙船のデザイン史は、半世紀にわたる人類の未来観の変化を、最も鮮やかに語ってくれるのです。
理想主義デザインの誕生 ― 1960年代の合理主義
1961年、ユーリ・ガガーリンが人類初の宇宙飛行に成功し、1969年にはアポロ11号が月面に降り立ちました。現実の宇宙船は銀色の円筒や球体で構成され、リベットやパネルがむき出しの“工学的な美”を放っていました。その実在するテクノロジーを、映画人たちは理想の象徴として映像化します。
1960年代は、宇宙そのものが「信仰の対象」だった時代です。人類が初めて地球の外へと到達し、科学が宗教に代わって未来を語ることができると信じられていました。そんな時代に生まれた宇宙船のデザインは、冷たくも美しい合理の結晶でした。代表作が、スタンリー・キューブリックの『2001年宇宙の旅』(1968)と、テレビシリーズ『スタートレック』(1966〜)です。
スタンリー・キューブリックはNASAの資料を徹底的に研究し、『2001年宇宙の旅』のディスカバリー号を「機能美の極致」として設計しました。ディスカバリー号は、棒状の船体に巨大な球体の司令部を連結した構造を持ちます。空気抵抗を考慮する必要のない宇宙空間で、機能だけを突き詰めた“無駄のない美”が特徴です。映画の美術チームはNASAの協力を得て、実際の宇宙開発計画を参考に設計図を描き上げました。その結果として生まれたのは、機械でありながらどこか神殿のような荘厳さを湛えた宇宙船でした。無音の宇宙を進むその姿は、人類理性の象徴であり、同時に人間の傲慢さへの警告でもあります。
一方、『スタートレック』のU.S.S.エンタープライズ号は、より親しみやすい理想を体現しています。デザイナーのマット・ジェフリーズは、航空機の構造をもとに“現実に存在しそうな未来の船”を目指しました。円盤型の主船体と二本のエンジンナセルという独自のバランスは、どこか安定感を感じさせます。エンタープライズ号のフォルムには、戦闘艦ではなく“探査船”としての理念、つまり「未知を恐れず、理性の光で宇宙を照らす」という時代の理想主義がそのまま刻まれているのです。
理想主義から現実主義へ ― 1970年代の転換点
1960年代の終わり、アポロ11号が月面に立った瞬間、人類は“理想の到達点”に到達しました。しかし、その熱狂は長くは続きませんでした。1970年代に入ると、宇宙開発は「夢」から「維持」の時代へと移り変わっていきます。アポロ計画の終了後、NASAはスカイラブやスペースシャトルといった“運用型”の宇宙活動へ舵を切り、宇宙は英雄たちの舞台ではなく、作業員たちの職場としての顔を見せ始めました。この変化は、映画の中の宇宙船デザインにも大きな影響を与えます。
この時期に登場した『スペース1999』(1975)のイーグル輸送船は、まさにその象徴です。白い骨格のような外装と、中央部に取り付けられた交換式モジュール。華やかさはありませんが、構造の一つひとつに“作業”の痕跡が感じられます。デザイナーのブライアン・ジョンソンは、実際の月面探査車両や宇宙作業機器を参考にしており、イーグル輸送船は「機能のために生まれた形」という意味で、当時としては異例のリアリズムを備えていました。
それまでの宇宙船が「科学の象徴」だったのに対し、イーグルは「労働の道具」へと変わりました。無菌的な理想空間から、少し埃っぽく、油の匂いのする現場へ。こうした現実的な発想がやがて、『スター・ウォーズ』や『エイリアン』といった作品の「現実主義」デザインへとつながっていきます。
現実主義デザインの台頭 ― 1977〜1980年代の反理想主義
1970年代後半、映画の中の宇宙は、もはや夢でも理想でもなくなりました。アポロの栄光はすでに過去のものとなり、現実の宇宙開発は予算削減や政治的制約に直面していました。ここから生まれたのが、現実主義デザインの黄金期です。
その転換点となったのが、1977年公開の『スター・ウォーズ』です。ミレニアム・ファルコン号は、これまでの宇宙船の常識を根底から覆しました。機体は非対称で、修理跡や焦げ跡が随所に残り、船内は配線や工具が散乱しています。監督のジョージ・ルーカスは、未来を「ピカピカの理想世界」ではなく「現実の延長」として描きたいと考え、デザイナーたちは中古車や工業機械のパーツを組み合わせて船体を作りました。ファルコン号は完璧とは程遠いデザインですが、だからこそ“人が生きている空間”の匂いをまとっていたのです。
この発想は、その後のSF映画全体に決定的な影響を与えました。特に『エイリアン』(1979)は、その極致といえる作品です。貨物船USCSSノストロモ号は、もはや探査船でも軍艦でもありません。企業に雇われた労働者たちが、宇宙の片隅で資源を運ぶ“宇宙トラック”です。内部は薄暗く、蒸気が漏れ、パイプがむき出し。船体には油と錆が染み込み、宇宙はもはや崇高な探求の場ではなく、閉塞した労働空間として描かれます。
ノストロモ号の設計を手がけたロン・コッブは、機能主義を徹底した工業デザインを導入し、そこにH.R.ギーガーの有機的な造形が融合しました。『2001年宇宙の旅』の宇宙船が「理性の神殿」だったとすれば、ノストロモ号は「現代社会の縮図」でした。理想主義の終焉を象徴するその姿は、以後のSFに決定的なリアリティを与えたのです。
再び理想へ ― 21世紀の宇宙船デザイン
20世紀の終わり、宇宙開発は新しい段階に入りました。1998年に国際宇宙ステーション(ISS)の建設が始まり、人類は初めて「宇宙に住み続ける」ことを実現します。そこにあるのは、かつての理想ではなく、配線やパネルがむき出しの現場的な空間です。しかし同時に、その構造の中には“共存”という新しい理想が生まれつつありました。21世紀の宇宙船デザインは、この「現実と理想の再接近」を映し出すものへと進化していきます。
その代表例が、クリストファー・ノーランの『インターステラー』(2014)です。エンデュランス号は、12個のモジュールを円環状に連結したデザインで、回転によって人工重力を発生させるという科学的に正確な設定を持っています。デザイン監修には理論物理学者キップ・ソーンが参加し、現実の工学原理に基づいた「ありうる未来の船」として構築されました。ディスカバリー号が象徴した冷たい理性の未来像を受け継ぎながら、エンデュランス号には“人間の感情”が宿っています。円環構造は、時間・重力・絆の循環を象徴し、理想主義の再生を新しい形で体現しているのです。
同じく、リドリー・スコット監督の『オデッセイ』(2015)に登場するハーミーズ号も、実在性を極限まで追求した宇宙船です。ソーラーパネルと回転居住区を備えたそのデザインは、NASAの実際のエンジニアが設計監修に関わっており、現代の宇宙技術でも実現可能な構造を持っています。ここで描かれる宇宙は、もはや神秘でも恐怖でもなく、科学者や技術者たちの日常的な現場です。彼らの作業と友情、そしてユーモアによって生き延びる人間の姿が、宇宙船のデザインそのものに重なっています。
理想と現実が対立するのではなく、互いを補い合う関係として融合し始めた――それが、21世紀の宇宙船デザインの特徴といえるでしょう。
理想と現実の対立 ― 宇宙船デザインが語る宇宙探査の歴史
こうして見ていくと、宇宙船のデザインは単なる造形ではなく、時代の精神の投影そのものです。理想主義が科学の夢を描き、現実主義がその夢の後始末をし、そして現代はその両者の和解を模索している――この往復運動の中で、宇宙船デザインは常に宇宙探査の現在地を映してきました。
そして、ここで取り上げなかった数多くの宇宙船たちも、それぞれの物語世界において強い「人格」を持っています。『スタートレック』のクリンゴン艦〈バード・オブ・プレイ〉は、戦士民族の誇りと攻撃性を体現し、同じ宇宙を航行していながらエンタープライズ号とは対照的な“闘争の理想”を象徴しています。『ファイアーフライ』のセレニティ号は、スクラップのようにくたびれた船体でありながら、独立心と自由を愛する乗組員たちの魂そのものです。他にも都市の監視社会を象徴するような『ブレードランナー2049』のスピナーなど、こうした多様なデザインの一つひとつが、単に世界観の一部ではなく、物語の登場人物の延長として機能しているのです。
宇宙船は、操縦される“道具”でありながら、物語の中ではしばしば「もう一人の主人公」になります。そのフォルム、傷跡、光の反射ひとつまでが、乗り手の性格や信念、そして時代そのものを語っているのです。
いかがでしたでしょうか。
次回は、「宇宙映画11.宇宙に響く「音」:SF映画において音楽はどのような役割を果たしてきたのか?」と題して、宇宙映画の「音」の歴史に迫っていきます。お楽しみに!