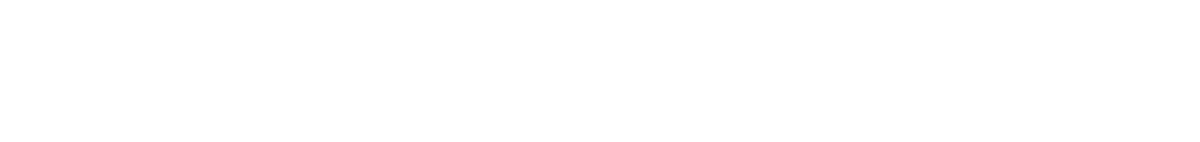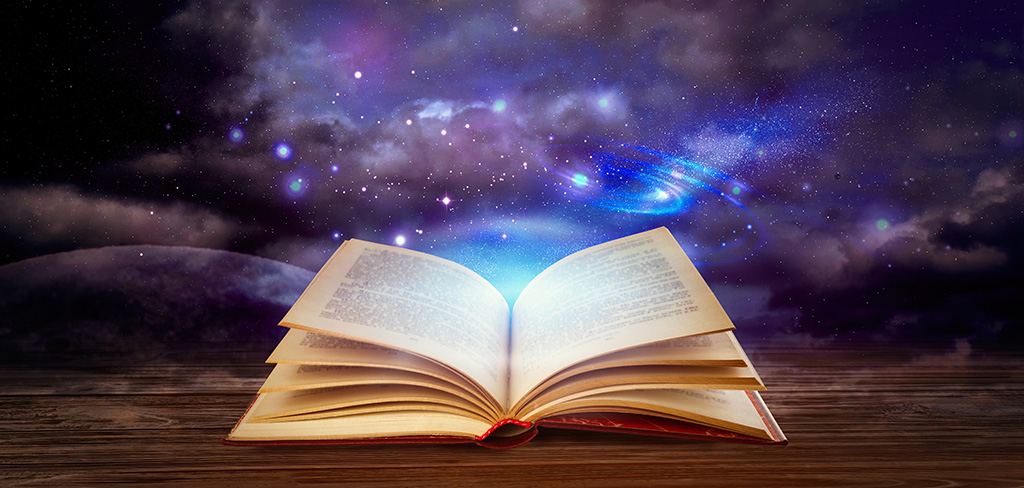イントロダクション:遠未来ビジョンの深層底流
宇宙小説シリーズの第11回は、ちょっと毛色を変えて「虚無の中で知性はどこまで生き延びるのか?」というテーマでお届けします。ここで取り上げるのは、単なるSF小説の紹介にとどまりません。宇宙を舞台に人間の意識やAIの未来を描いた作品を手がかりに、背後に流れる哲学や思想の潮流をたどっていきたいのです。
その源流のひとつが、19世紀末のロシアに生まれた「ロシア宇宙主義」。ニコライ・フョードロフという思想家は、人類の使命は死者を科学的に復活させ、宇宙へと拡散していくことだと説きました。突拍子もない話に聞こえますが、この「人間を超えるビジョン」は、のちのソ連SFや現代の宇宙開発論にも大きな影響を与えています。
現代に目を向けると、イーロン・マスクの「人類を火星へ」、そして元哲学徒にして異端の実業家ピーター・ティールの「人間をアップデートする思想」にも、この流れを受け継ぐ部分が見えてきます。背景にあるのは「ポストヒューマニズム」と「加速主義」と呼ばれる哲学。テクノロジーを推し進め、人間を超えた存在へと進化させるべきだという立場であり、SFの中で繰り返し描かれてきたテーマでもあります。
今回は、フョードロフの『共通事業の哲学』を出発点に、アーサー・C・クラーク『都市と星』、グレッグ・イーガン『ディアスポラ』を取り上げながら、SFと哲学、そして現実の未来像がどのように響き合っているのかを考えていきましょう。
ニコライ・フョードロフ『共同事業の哲学』(1906)
https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309231419/
まずご紹介したいのは、SFという枠を少しはみ出してしまうかもしれませんが、ポストヒューマニズムや宇宙SFの源流として外せない哲学書です。ニコライ・フョードロフの『共同事業の哲学』。
この本は小説ではなく哲学的な構想なのですが、20世紀以降の宇宙SFに決定的な影響を与えたといっても過言ではありません。フョードロフが描いた人類の未来像は、科学小説やスペースオペラが誕生するよりもはるか前に、「宇宙スケール」で人類の運命を考えるものでした。
彼の主張はとにかくラディカルです。人類の究極的使命は「すべての死者を復活させること」、そして「宇宙全体を調和的に支配すること」だと説いたのです。死者の復活と聞くと宗教的な響きがありますが、フョードロフはあくまで科学的手段によってこれを達成すべきだとしました。
当然、復活した人類は人口が爆発的に増えます。そのため地球にとどまるのではなく、宇宙へと拡散していかなければならない。――この発想は、まさに現代のイーロン・マスクが語る「火星移住」や「人類の多惑星種化」に直結しているように思えます。
この「人類の宇宙的運命」というビジョンは、ツィオルコフスキーをはじめとするロシア宇宙主義者や、イワン・エフレーモフらソ連SF作家たちに引き継がれました。そして今なお、AIや宇宙開発をめぐる議論の背後で、深い影響を及ぼし続けています。
アーサー・C・クラーク『都市と星』(1956)
https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000610367
フョードロフが「全人類の復活と宇宙への拡散」という壮大な使命を語ったのが19世紀末だとすれば、20世紀半ばにクラークが描いた『都市と星』は、そのビジョンをテクノロジー的に換骨奪胎した物語だと言えます。舞台は、人の生と死さえも完全に管理された未来都市ダイアスパー。ここでは人々が千年の寿命を終えると都市のメモリーバンクに記録され、数万年後に再び肉体を与えられて「復活」します。結果として人類は死を超え、文明は安定しきった状態を手にしているのです。
けれども、それは本当に「進歩」なのでしょうか。変化も冒険もない世界に生きることは、果たして人間的な幸福なのか。主人公アルヴィンは、ダイアスパー唯一の「異端児」として、都市の外の世界や人類の失われた歴史に向かって冒険に踏み出していきます。この構図は「加速か停滞か」という問いそのものであり、ポストヒューマニズム的に考えるなら「死や進化を超えた存在は、それでも人間と言えるのか?」という問題を突きつけてきます。
クラークの描いた都市は、単なる未来都市ではなく、サイバネティックスや情報理論が生まれたばかりの時代における最先端のイメージでもありました。人間の生死を「データ」として管理し、都市そのものを巨大なメモリーバンクとして描いた発想は、インターネットやクラウド、AIによる意識の保存といった現代的なテーマを予見していたと言えるでしょう。さらには、仮想空間に囚われた人類という構図は、のちの『マトリックス』に直結するほどの先見性を持っています。
『都市と星』は「停滞の果てにある永遠の安定」と「未知への冒険」という対立を描きながら、人類が変化をやめることの危うさを問いかけます。これはまさに、フョードロフが提唱した「人類の宇宙的使命」をテクノロジーの言語に翻訳し直した一冊であり、また現代の加速主義的未来論とも強く響き合うのです。
グレッグ・イーガン『ディアスポラ』(1997)
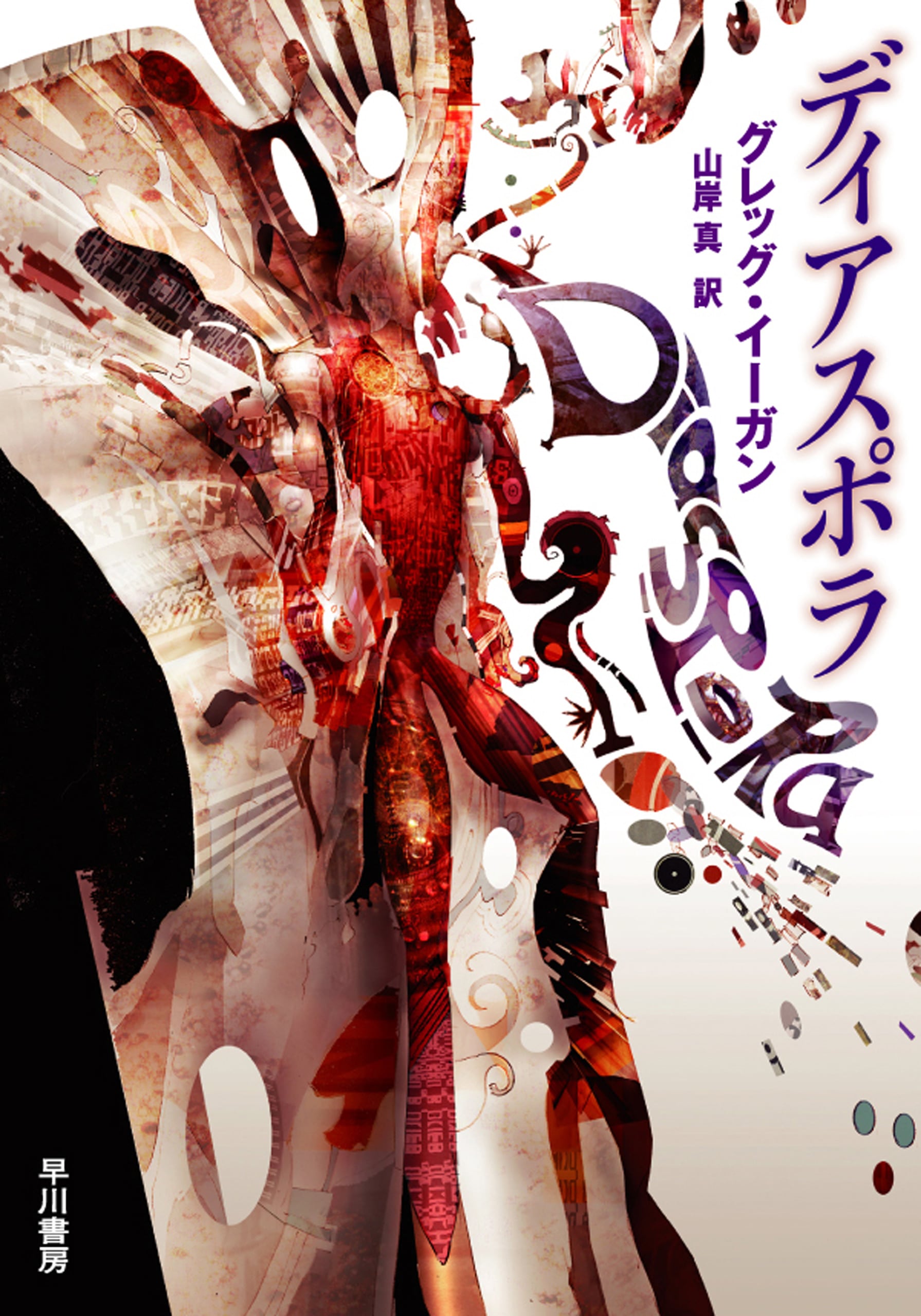
そして最後に紹介するのが、オーストラリアの作家グレッグ・イーガンによる大作『ディアスポラ』です。1997年に刊行されたこの小説は、人類がいかにして宇宙に広がり、虚無の中で知性を生き延びさせるのかという問いに、冷徹かつ壮大な答えを与えてくれます。
人類は果たして「有人」での恒星間旅行を実現できるのか? この問いに対して、イーガンはまず「できない」と切って捨てます。なぜなら、地球から最も近い恒星系であるケンタウルス座アルファでさえ4.4光年先。冷凍睡眠や世代宇宙船ではあまりに非現実的で、有限の肉体を持つ存在には恒星間航行はほぼ不可能だからです。ではどうすればよいか。イーガンが提示した答えは「意識そのものをソフトウェア化し、物質的身体を超える」というものでした。
本作に登場する人類は大きく分けて三種類います。旧来の肉体を保持した「肉体人」、人格を完全にソフトウェア化して仮想空間で生きる「ポリス市民」、そしてそのデータを機械の身体に受肉させた「グレイズナー」。特にポリス市民は、巨大スーパーコンピューター=「ポリス」の内部で暮らしており、物理的時間とは切り離された独自のコンピューター時間「タウ」を生きています。彼らは仮想空間の「観境」を呼び出すことで思考のままに移動でき、物理的制約から完全に解放されています。
ただし、必要に応じて物理世界に再登場することも可能です。ポリス市民が機械の身体に宿って活動する姿が「グレイズナー」です。久々に肉体感覚を得た彼らは、ぎこちなく歩き、触れ合い、握手を交わしながら、「有限な物理的存在であることの面白さ」を再発見します。その様子を「肉体人」たちが奇異の目で眺める場面は、現代の私たちにも強烈な違和感と共感を同時に与えてくれます。
この多様な存在形態を背景に、物語は何千年にも及ぶ宇宙の旅へと展開していきます。ポリスを搭載した小型宇宙船は、仮想的に構築されたミニワームホールを利用して超光速航行を実現。寿命や資源の制約を超え、恒星間を渡り歩くことが可能になったのです。ここに描かれるのは、単なる宇宙冒険ではなく「人間とは何か」という問いそのものの更新です。
もちろん、この前提には議論があります。「人格は本当にソフトウェア化できるのか?」という問題です。イーガンは唯脳論的前提を極限まで突き詰める作家ですが、必ずしも単純な唯脳論者ではありません。むしろ、計算過程の中に量子的・超物理的な要素が関与している可能性をほのめかしています。ここで思い出されるのが、ロジャー・ペンローズの「量子脳理論」。神経細胞レベルでは説明できない意識の特異性を、量子論的効果に求めたこの理論は、イーガンの提示する「データ化された意識」に別の深みを与えてくれます。
もしペンローズ的な「量子的意識」を『ディアスポラ』の世界に持ち込むならどうなるでしょう。単なるプログラムではなく、量子効果が生み出す不可測のゆらぎが「人間性」を保証する要素になるのかもしれません。ベルクソンが語った「物質界の秩序」と「生命界の秩序」が、量子論の次元で奇妙に交差する。その可能性を本作は強烈に予感させます。
イーガンが描いたのは、人間の概念そのものをアップデートすることで初めて宇宙規模の冒険が可能になる未来です。肉体にとどまる限り恒星間航行は夢物語に過ぎませんが、意識をデータ化し、AIや物理法則を利用して「虚無の宇宙を漂う知性」へと変貌すれば、その夢は現実になるかもしれない。『ディアスポラ』は、ポストヒューマニズムと加速主義が到達しうる究極の未来像を、SFの枠を超えて私たちに突きつけてきます。
最後に:加速する未来、問い直される人間性
ここまで見てきた三つの作品──フョードロフ『共同事業の哲学』、クラーク『都市と星』、イーガン『ディアスポラ』──は、それぞれ異なる時代に書かれながらも、一本の思想的な線で結ばれているように思います。
19世紀末、フョードロフは人類の使命を「死者の復活」と「宇宙への拡散」という、常識を超えた形で語りました。彼の構想はロシア宇宙主義を生み、ツィオルコフスキーやソ連SFに受け継がれただけでなく、イーロン・マスクの火星移住計画や「人類は多惑星種でなければならない」という現代的スローガンにもつながっています。人類を宇宙に押し出す「思想の推進力」として、フョードロフの幻視はいまなお生きているのです。
20世紀半ばのクラークは、テクノロジーの言語でその問題を翻訳しました。『都市と星』に描かれるダイアスパーは、人間が死や進化すらもコントロールできる「究極の管理社会」。そこでは安定が保障され、永遠の命すら約束されていますが、同時に人間らしい冒険や成長は失われています。クラークが投げかけたのは、「進歩の停止は本当に幸福なのか?」という問いです。これは加速主義の根幹にある「技術は止められないし、止めるべきではない」という考え方と響き合い、現代のAIやシンギュラリティ論の議論にも直結してきます。
そして20世紀末、イーガンはその問いを極限まで推し進めました。『ディアスポラ』では、肉体を持つことをやめ、人格をソフトウェア化し、時間や空間の制約を超えた存在が描かれます。彼らは数千年にもわたり恒星間を旅し、虚無の宇宙を知性の力で生き抜いていく。そのビジョンは、人間を「アップデート可能な情報」として捉え直すポストヒューマニズムの到達点を示しています。
こうして振り返ると、三つの作品はまるで思想のリレーのように見えます。
現代に目を向ければ、シリコンバレーの未来論、ピーター・ティールの投資思想、イーロン・マスクの宇宙開発は、この流れを現実のビジネスや政治に引き戻したものだと言えるでしょう。テクノロジーの進歩が人間の枠組みを超えようとする動きは止められず、むしろ加速していく。ポストヒューマニズムや加速主義という哲学的立場は、SFにとどまらず、すでに私たちの社会の現実そのものを形作り始めています。
これらのSF作品を読み解くことは、単なる未来小説を味わうことではなく、「私たちの文明はどこへ向かうのか?」という問いを自分自身に返すことでもあるのです。虚無の中で知性はどこまで生き延びられるのか。SFは、その答えを先取りする壮大な実験室であり続けているのだと思います。