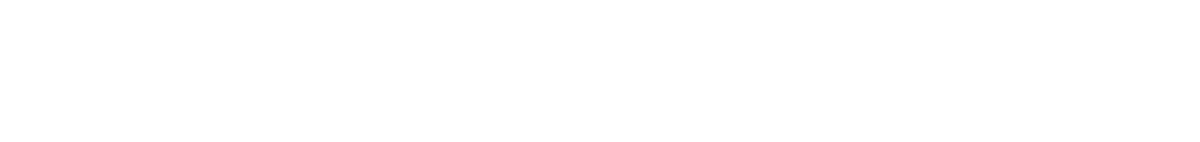イントロ 宇宙映画よりもっとディープ。宇宙小説の「エイリアン言語」を紹介しよう
前回の記事では、スター・トレックのクリンゴン語や『アバター』のナヴィ語など、映画に登場するエイリアン言語を紹介しました。今回は少しフィールドを移して、「宇宙小説」におけるエイリアン言語を見ていきたいと思います。
映画と違って、小説という媒体は、文字だけで世界を立ち上げるぶん、言語そのものの構造や、言語が人間の認知に与える影響までじっくり描くことができます。ある言語は二人の声が重ならないと成立せず、ある言語はそれを身につけた話者の時間感覚を変えてしまい、ある言語はそのまま「戦争兵器」として設計されています。さらに、そもそも言語という概念をほとんど持たない高度文明すら登場します。
ここでは、そうした多様なエイリアン言語を描いた宇宙SF小説のなかから、知的に興味深い視点を提示している5作品を取り上げてみます。それぞれ、どんなふうに「宇宙言語」が描かれているのか、ざっくりと見ていきましょう。
チャイナ・ミエヴィル『言語都市』 二人の「和声」でないと言葉にならない言語
チャイナ・ミエヴィル著『言語都市』に登場するエイリアン〈ホスト〉の言語は、かなり異常な設定になっています。彼らは二つの声帯を持ち、二人一組で同時に発話しないと、ちゃんとした「文」になりません。
人間側はそれに対応するために、遺伝子操作でほぼ同一のクローンのような双子を作り、「アンバサダー」として育てます。この二人が寸分違わずハモることで、ようやくホストたちとコミュニケーションが取れる、という仕組みです。
この言語のやっかいなところは、「嘘がつけない(そもそも虚構を表現できない)」「比喩やメタファーを理解させるには、「実際にその出来事を再現して見せる」必要がある」という点です。物語の中で、「比喩」や「嘘」にあたる表現がホストたちの社会に投げ込まれたとき、それはまるでドラッグやウイルスのように機能し、文明そのものを揺さぶっていきます。
ここでは、言語は単なるコードではなく、真理と虚構の境界そのものとして描かれます。二人の声が揃わないと「言語」にならない、という設定も含めて、「言葉の成立条件」を根本からひっくり返している作品です。
テッド・チャン『あなたの人生の物語』 言語を身につけると、時間の見え方が変わる
テッド・チャンの代表作『あなたの人生の物語』に登場するヘプタポッドBは、言語が認知OSを書き換えるというアイデアを極限まで押し広げたものです。
ヘプタポッドBは、我々のように「左から右へ」「過去から未来へ」と線形に文章を組み立てていくのではなく、一つの文を最初から最後まで“同時に”書き上げるという不思議な円環構造を持っています。ここにおいて文を理解することは、その出来事の「始まりから終わりまで」を一度に把握する行為に近くなります。
主人公の言語学者がこの言語を習得していく過程で、彼女の時間認識は徐々に変質していきます。時間は一本の線ではなく、すでに完成している曲線を、別の角度から眺め直すようなものになっていきます。その結果として、「未来の記憶」が生じる、という展開(ここではネタバレはしません)につながります。
ここで描かれているのは、「ことばは世界のラベルではなく、世界の見え方そのものを変えるインターフェースなのだ」という、有名なサピア=ウォーフの仮説に似た発想です。言語そのものが、世界の見方を変えてしまうのです。
アン・レッキー『叛逆航路』 複数の身体に宿るAIが語る「多視点のわたし」
『叛逆航路』に登場するAIは、ひとつの意識が複数の身体に同時に宿る、という設定になっています。
かつてこのAIは巨大な宇宙戦艦であり、その船体のほかに、「アンシラリー」と呼ばれる人間の身体を多数接続し、一つの意識で複数の身体を同時に動かしていました。
作中では、このAIが語る「わたし」が、過去の多身体状態と、現在の単独の身体を行き来しながら物語を進めていきます。
読者は一人称で語られているはずなのに、その「わたし」が同時に何カ所にもいて、違うことを考え、違う行動を取っている、という奇妙な読書体験をすることになります。
ここで興味深いのは、AIが使う言語そのものというより、一人称の構造が壊れていく感覚です。通常、「わたし」はひとつの身体と紐づいていますが、この作品では、「わたし」が空間的にも時間的にも分裂しつつ、それでもなお「一人称」として語り続けます。同じ宇宙の出来事を、一本のカメラではなく、無数のドローン視点から同時に見ているような、不思議な一人称です。
現代では「AIにロボットの身体を持たせたらどうなるか」という思考実験が現実味を帯びてきていますが、無数の身体をAIに与えた際にどのような意識を持つに至るかは、まだ未踏の領域に留まっています。
サミュエル・R・ディレイニー『バベル-17』 高度に設計された人工言語が、戦争兵器になる
『バベル-17』に登場するバベル-17は、単なる暗号ではなく、完璧に設計された人工言語として描かれています。「語彙が厳しく削ぎ落とされているのに、少ない語数で高度で複雑な事象を表現でき、プログラミング言語のような論理性を備えている」という、ある意味「理想の言語」です。しかもこの言語には、一人称 / 二人称が存在しません。「わたし」と「あなた」という区別がない世界で思考するように、話者の頭を組み替えてしまうのです。
この言語を学んでしまった者は、無意識のうちに「敵」に対する攻撃欲求を抱くようになり、自己分裂的な行動を取るようになります。言語の構造そのものが、話者の認知と人格をハックする戦争兵器として機能しているわけです。ここにはどこか、「詩そのものが政治と戦争の中心にあった時代」への連想もあります。イスラム世界で詩人が部族間の名誉を左右したように、言葉の力がそのまま攻撃力として立ち上がってくるイメージです。『バベル-17』では、それが文字通り人の心を乗っ取るコードになっているところが怖いところです。
ここで触れておきたいのが、現実世界に存在する「設計された人工言語」の代表例、エスペラント語です。国際共通語を目指して19世紀末に作られたこの言語は、語彙や文法が極限まで整理されていて、「学習しやすい」「人類共通の言語になりうる」という理想を背負っていました。ある意味では、『バベル-17』が描いた“完璧な人工言語”の現実版と言ってもいいかもしれません。
そして、このエスペラント語の創始者であるザメンホフは、ポーランド系のユダヤ人でした。彼はユダヤ人迫害や民族対立のただ中で育ったため、人類が共有できる「中立語」を作ろうとしたわけです。言語によって争いを煽るのではなく、言語によって争いを減らすという、ある意味で『バベル-17』とは真逆の方向性を目指した取り組みでした。
ところが、歴史は皮肉です。スターリンをはじめとしたソ連の権力者たちは、エスペラント語を「ユダヤ人によって作られた危険なウイルス」のように恐れました。「国境や民族の壁を越えてつながるネットワークを作る言語」なんて、独裁体制からすれば最悪の悪夢です。結果として、1930年代にはエスペラント話者の多くが粛清の対象にもなりました。ちなみに20世紀初頭の日本や中国の知識人の中にもエスペラント運動は盛り上がり、中国の文学革命を率いた魯迅などはその中でも有名でした。
劉慈欣『三体』シリーズ 「嘘」を知らない文明と地球文明の邂逅
最後に取り上げるのは、Netflixでドラマ化されて大ヒットした『三体』シリーズに登場する三体文明です。ここでは、三体人という高度な宇宙文明が、「人間のような言語文化をほとんど持たない」存在として描かれます。
三体人は、身体そのものが情報発信の器官になっており、内面を隠すことができない“透明なコミュニケーション”を行っているとされます。テレパシーのようなものですね。そのため、先ほど紹介した『言語都市』にも似て、社会の中で「嘘をつく」という発想自体が育ちません。隠しごとや欺瞞を前提とした政治ゲームがほとんど成立しない世界です。対して地球側は、「書き言葉・話し言葉を通じて歴史や文学を蓄積し、比喩や物語やプロパガンダによって他者を操り、嘘や沈黙や曖昧さを駆使して生き延びてきた文明」です。
「嘘を知らない高度文明」と「嘘を前提とした人間社会」が接触したとき、どんな噛み合わなさが起きるか――『三体』はそのギャップも含めて、コミュニケーションの問題を描いています。
三体世界は、過酷な天体環境のせいで文明が何度もリセットされ、長期的な歴史や物語文化が育ちにくい環境にあります。その意味で、『三体』における三体人は、「言語が満足に発達できなかった場合の高度文明」という、少し怖い想像実験でもあります。
おわりに
ざっくりと5作品を見てきましたが、どれも「エイリアン言語」という一言では片づけられないくらい、言語そのものにラディカルな仕掛けが施されています。
「二人の和声でしか成立しない言語」「習得すると時間の見え方が変わる言語」複数の身体を同時に語る一人称」「話者の思考を直接ハックする戦争兵器としての言語」「そもそも「嘘」という発想がないコミュニケーション」。
こうして並べてみると、宇宙小説の中のエイリアン言語は、「もし、言葉がこういうふうにできていたら、世界はどう見えるか?」という壮大な思考実験の集積のようにも見